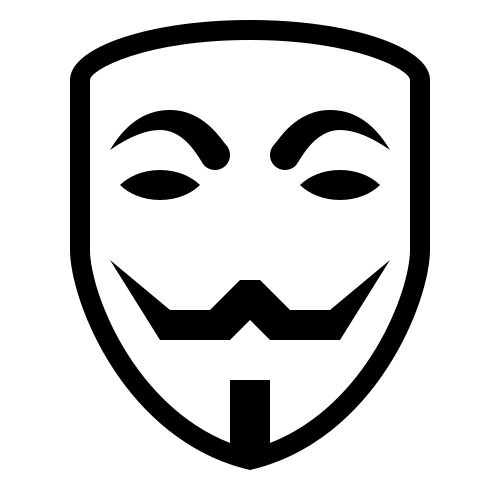前回の続き。『希望格差社会―「負け組」の絶望感が日本を引き裂く』を読み終わって蘇った記憶の二つめ。隆慶一郎氏の著書から少し長いけど引用します。
危険を危険としてありのままに受けとめ、素早くそれに対応する処置をさぐり、それが終わるとまた悠々と酒を飲む。誰一人無用の恐れ、無用の不安など示す者はいない。
[…]いずれも歴戦の武士である。つまり徹底した現実家である。現実家だから、危険に対しては敏感だ。だが危険は恐ろしいものだ、という風には、この男たちは考えない。危険は考慮し、対策を考え、対策のない時は極力それを有利に使おうと考える。ただそれだけのことだ。この男たちに恐怖心が欠如しているというのは間違いである。恐れるべき時には人並みに、いや、人並み以上に恐れる。ただ恐怖の先どりをしない。やがて起こるかもしれぬ恐怖の場面を脳裏に描いて、早々と恐れるということをしない。そんな恐怖心ぐらい寝もなく意味もないものはない、と心底思っているのだった。その時はその時のことだ。今は今である。だから、将来の危険は今の歓楽を少しも遮げることがない。
隆慶一郎 『影武者徳川家康 中巻』P.248-249
大学時代に隆慶一郎氏の書籍に出会い、むさぼるように読んだ。氏は、傾奇者、葉隠、道々の者、吉原などをテーマに傑出した伝奇小説を世に送り出した。いずれの書にも、「凛とした清々しい人物」が登場したのを憶えている。
なかでも、印象に残っているのは、「無縁」についてかな。「士農工商」の枠外の人たち。例えば、吉原の花魁、傀儡師、木地師、山窩、一遍上人といった人たちは、移動の民であり、『世間』と縁を切った人といわれていたんだよね。
花魁は自分の教養と身体、傀儡師は踊りや歌舞伎、木地師は木製の塗り物の椀や皿、盆の生産、山窩は竹細工、山の番人、川の漁撈を生業としていた。まさに己の身と才覚で生きていき、無縁の者だけで助け合い、『世間』で何があろうが知ったことではなかった。
毎日が「死」と向かい合い、誰も助けてくれないから、待っているのは文字通り「野垂れ死に」になってしまう。『世間』と縁を切った「無縁」になり、「野垂れ死に」する"リスク"をとってまで彼らが得たかった代償は、「自由」。
彼らは、「上ナシ」を標榜し、日本全国でどこでも移動ができた。本来なら各地に関所があって、通行許可書がないと移動できない時代なのに、「通行の自由」の免罪符があった。
ただ、時の幕府もこんな人ばかりが出現しては、困るから「士農工商」よりさらに下の階層を設けた。そして、士農工商の民に、「今の身分からはみでると、ああなるぞ」という「脅し」と「今の身分に満足すれば、つらいけど安定した生活が送れるぞ」という「安心」を与えていたように思う。だからこそ便宜上、彼らは『世間』から見ると、「人間ではないような」扱いを受けたのではないかな。
まぁ、希望格差社会のレビューは後日書きたいと思うけど、頻繁に登場する「リスク」について、自分には少し違和感があった。その違和感を、混沌としながらも自分なりにまとめると、過去の漂白の民・道々の者にいきついた。
己の才覚一つで生きていく難しさは、過去の人が証明してくれている。いつの世もそのことは変わりのない現実として隠然と存在しているんじゃないかって、思った。
何か中途半端なエントリーだなぁ。こんな日もあるということで許してたもっせ。