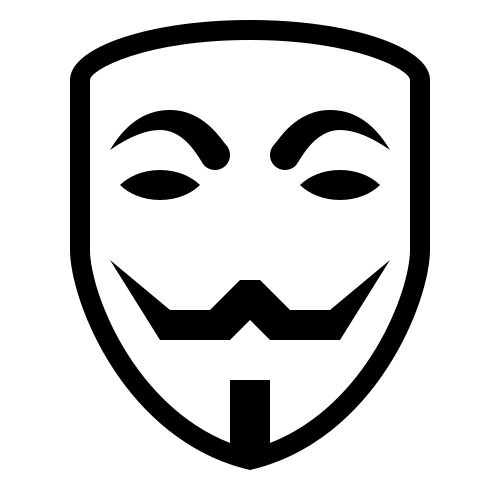著者は藤原正彦先生。先生の著書、『遥かなるケンブリッジ―一数学者のイギリス』、『天才の栄光と挫折―数学者列伝』、『数学者の言葉では』を読了して(そういえばレビューしていないかも)、すっかり魅了されていたので発売日に購入し、一気読み体制が整うまで”積ん読棚”に奉っていた『国家の品格』。内容についてはカバー表紙の説明に集約される。
著者は藤原正彦先生。先生の著書、『遥かなるケンブリッジ―一数学者のイギリス』、『天才の栄光と挫折―数学者列伝』、『数学者の言葉では』を読了して(そういえばレビューしていないかも)、すっかり魅了されていたので発売日に購入し、一気読み体制が整うまで”積ん読棚”に奉っていた『国家の品格』。内容についてはカバー表紙の説明に集約される。
日本は世界で唯一の「情緒と形の文明」である。国際化という名のアメリカ化に踊らされてきた日本人は、この誇るべき「国柄」を長らく忘れてきた。「論理」と「合理性」頼みの「改革」では、社会の荒廃を食い止めることはできない。いま日本に必要なのは、論理よりも情緒、英語よりも国語、民主主義よりも武士道精神であり、「国家の品格」を取り戻すことである。すべての日本人に誇りと自信を与える画期的提言。
「すべての日本人に誇りと自信を与える画期的提言」には、あえて愚見を述べたいが、それは後ほど。
藤原正彦先生は東京大学理学部数学科を卒業された数学者だ。公理系の論理、「1か0」の論理に身を染めきったいわば「論理の化身」の先生が、なぜ「論理」よりも「情緒」と強く主張されるのか?
本書の中身は、この「論理より情緒」の命題に対する証明につきる。留学体験から学んだ西洋社会と、帰国して大学教授の職に就いた日本社会を比較・分析しながら、「論理より情緒」に至った思考の経緯を述べている。
本書を一言で集約するのは失礼千万であるが、蛮勇をふるうなら、「情緒を育てるには武士道精神が必要だ」が先生の主張である。
表題の『国家の品格』をそなえるためには、条件が3つある。かつての日本は3つの条件を満たしていた。満たしていたのは、「武士道精神があったから」という帰結になる。だから武士道精神を疎かにした日本は、国家の品格を著しく失墜させてしまったという危惧から本書を執筆されたのであろう。
例えば「英語よりも国語」の話をとりあげてみる。国際人を育てるために英語が必要だと文部科学省は言う。それには、旧来の英語教育ではダメだ、だったら小学校から英語を学ばせようと。
その論理を一蹴する。先生は、国内外問わず”国際人”といわれる方々との人脈を持っておられる。それらの交流から得た経験談を援用して論破する。
研究生活時代、数学界のノーベル賞と呼ばれるフィールズ賞を受賞したケンブリッジ大学の大教授が、「夏目漱石の『こころ』の中の先生の自殺と、三島由紀夫の自殺とは何か関係があるのか」と尋ねた。
他にも、ロンドン駐在の日本人商社マンが現地のビジネスマンに夕食に招かれた際、こう尋ねられた。「縄文時代と弥生土器はどう違うんだ」「元寇というのは二度あった。最初のと後のとでは、何が違ったんだ」
先生が言うには、イギリス人の陰険な性質を差し引いても世界のトップ・エリートというのは、いきなりそういうことを訊いてくるのだそうだ。決して、自国(ここではイギリス)の歴史やシェイクスピアのことなんて訊かない。
だから日本人としての教養を身につけなさいと警鐘する。それには、国語が何よりも大切なのだと。なぜなら「思考と言葉」がほとんど一致するからだ。自国の言葉でまともに考えられない、自国の文化や歴史に精通していない人物が、英語で「ものを語る」など何をいわんやというほどの勢いである。
他にも、「何の理由もない、駄目なものは駄目。無条件にいけないものはいけないんだ」という”教え”を論理抜きにたたき込まれた、といったご自身のお父上の教育論を披露する。
ここでは具体的な挿話を紹介したが、本書では「論理がいけないのではなく、論理だけでは通用しない」という理由を説いている。それらの一つ一つは、明晰な文章であるからとてもわかりやすい。
ただし、最初に書いたように「すべての日本人に誇りと自信を与える画期的提言」という出版社の宣伝にあえて苦言を呈したい。
「論理に成熟した情緒」と「論理に未熟な情緒」を混同した宣伝文ではないか。
先生のように「論理の甲乙」を熟知しているからこそ「情緒」という感性のすばらしさを達観できるのだと思う。それを安易に受け取れるような宣伝文によって、「何だやっぱり古き良き時代がいいじゃないか」と脊髄反射したなら早計だろうし、それを煽ってはいけない。
「論理に未熟な情緒」をかろうじて持っている(と願っている)愚生は、易々と「情緒」に頼ってしまっては危険だと思う。マスコミの報道によって世論が180度かわってしまうこともあると想定するなら、「論理」を身につける努力を少なくとも忘れたくない。
話が主観的な方向へ逸れてしまったが、本書の具体的な例示には、藤原正彦先生がどんな知識を体得し、どの分野の書籍を読んでこられたのかがわかる。そういった理由からも、教職に就く方々にオススメしたいし(各人がどう判断するかは別として)、もし自分に子どもがいるなら父親として真っ先に読んでみたい一冊だ。