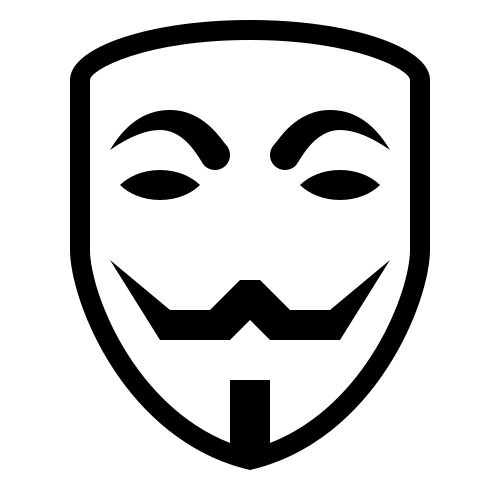原作を読みたいと思っていたら、先にDVDを買ってしまった。1975年度アカデミー賞主要5部門を独占した名作。レビューの多くがラストシーンを絶賛。個人的にはそう思わない。とにもかくにも、「この出演者たちのような演じ方を演技と称するのかなぁ」と目を奪われた。余談、愚生はDVDをレンタルしない。同じ映画を何十回と観るので購入する。フレームワーク・色彩・台詞・イースターエッグ・シンボリックなどなどを学びたいので、どうしてもそうなってしまう。このレビューは初見で書いている。
原作を読みたいと思っていたら、先にDVDを買ってしまった。1975年度アカデミー賞主要5部門を独占した名作。レビューの多くがラストシーンを絶賛。個人的にはそう思わない。とにもかくにも、「この出演者たちのような演じ方を演技と称するのかなぁ」と目を奪われた。余談、愚生はDVDをレンタルしない。同じ映画を何十回と観るので購入する。フレームワーク・色彩・台詞・イースターエッグ・シンボリックなどなどを学びたいので、どうしてもそうなってしまう。このレビューは初見で書いている。
1963年9月のある日。オレゴン州立精神病院にひとりの男が連れられてきた。ランドル・P・マクマーフィ。彼は刑務所の強制労働を逃れるために狂人を装っていた。しかし、精神病院はもっと悲惨な状況にあった。絶対権限を持って君臨する婦長によって運営され、患者たちは無気力な人間にされていたのだ。さまざまな手段で病院側に反抗しようとするマクマーフィに、患者たちも心を少しずつ取り戻し始めた。そんな彼の行動に脅威を感じた病院は、電気ショック療法を開始するが、マクマーフィも脱走を計画し始める……。『カッコーの巣の上で』
映画史や映画批評について無知なので、アメリカン・ニューシネマと言われてもピンとこない。鑑賞後、Wikipediaに聞いてみた。なるほど、そんな社会背景から制作された映画かと納得。
ジャック・ニコルソンの演技に終始圧倒された。「精神異常を装って刑務所での強制労働を逃れた男」を演じている。「精神異常を装って」ということは、「正常」と「異常」(医学的に適切な表現かどうかはご容赦)を外面と内面で使い分けている。
下劣な表現をすると、「目が逝っている」のがよくわかる。「正常」と「異常」を目で演じているのだろうか。正直、寒気立った。どっちがほんとうのジャック・ニコルソンなんだと。
派手な映像や凝った大道具はない。でも観客を魅了する「何か」がある。プロットで勝負し、演技力そのものを映像化している中にある「何か」。それは、必要以上に盛り込まれていない台詞や、人物へのクローズアップを多用するあたりから感じ取れる。唐突で恐縮だが、古畑任三郎の「偽善の報酬」で加藤治子が、「今の映画はみんなしゃべりすぎよ」って罵るラストシーンを思い出した(ちなみに、mixiのプロフィールにも書いているが、古畑任三郎フリークです)。
他の出演者もすばらしい。若いBrad Dourifに驚いた(中年になってからの映画しか見たことなかったので)。彼の役柄は、母親に入院させられた青年。どもりながら話し、母親と看護婦長に対し、異様に畏怖しているさまを眺めると、監督が絶賛したのもうなづける。Danny DeVitoが出演している。この人の演技は他の映画でもQED。本作でもすばらしい脇役に徹している。ニコニコしているだけなのに存在感がある。
一番印象に残ったシーンは、ジャック・ニコルソンがみんなを連れ出して、船に乗って海へ釣りにでるくだり。クルーザーを無断借用しようとしたとき、管理人が「何をしている」と一喝。すると、ジャック・ニコルソンは、「精神科の学会の集まりなんだ」と言って、一人一人の名前に「博士」の冠をつけて紹介する。そして、各人の顔がアップに。なんとなく自信に満ちあふれた表情をしている(自分がそう感じ取っているだけだが)。
そのシーンを観ている自分が不思議だった。「博士」と紹介されるだけで、みんなを見る目がなんとなく変わる。カメラワークがその変化を強調しているせいもあるが、「博士」が付くときと付かないときの顔の表情に魅せられた。これが映像が伝える妙なんだなぁと感嘆した。
収録されている解説によると、エキストラは実際の患者を採用し、病院で撮影している。出演者も数週間、病院で生活し、患者の立ち居振る舞いにふれている。
方々でのレビューにあるとおり、テーマが「完全統制と自由、社会の不条理」であり、そこへロボトミーというメッセージを添えているので、さまざまな感情や論理を問いかけてくる。また、原作とは少し異なる解釈がされるあたりも、映画ならではの演出があるからかもしれない。
最後に、ぜんぜんとんちんかんな感想。英語がやさしい。矛盾して恐縮だが、英会話ができない愚生でも聞き取れて、意味が理解できる。だから、ヒアリングの勉強もかねてこれから何度も味わってみたい。