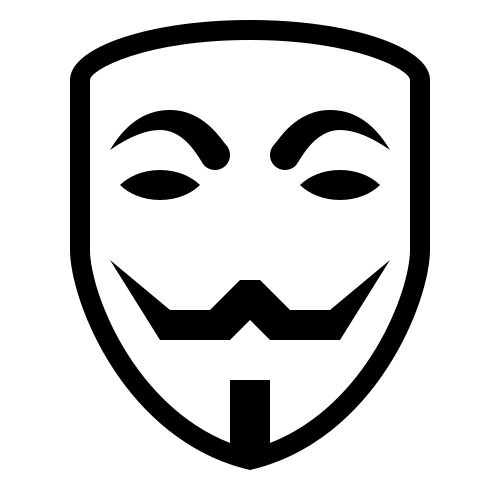昨年読んだ『男たちへ』がやたら身体にまとわりつく。確か、ずいぶん前に紹介したなぁと思って、自分のサイトを検索してみると、なんと、9/15にポストしていた。何の因果か、奇遇というか、1年経っても成長していないというか。情けなくなる。と、我が戯れ言はどうでもよいとして、何がまとわりつくのか。それが、「顔」である。
三十代の男たちとなると、彼らのその後の見当がだいたいつくようになる。なにかやれそうか否かが、ほとんどわかるようになってくるのだ。それが四十代ともなると、もう明白である。話を少ししただけで、これは幸福な人生を歩むかそれとも不幸で終わるかが、相当に高い確率で予測できるくらいだ。そして、十年経つと、私の予測はだいたい当たっている。これは顔にもでてくるからである。いくつだったろうか、男は自分の顔にも責任をもてという年は。
美醜ではない。はっきりとは言葉で言いあらわせないが、一種の空気である。その人が自然にかもしだす、雰囲気のようなものである。これは、私にもわかるくらいだから、他人には感じられるものであるにちがいない。『男たちへ―フツウの男をフツウでない男にするための54章』
この「一種の空気」とは何なのだろうか?—–これがまとわりつく。いくつの頃からかとんと覚えていないが、他人の「顔」が気になるようになった。ただなんとなく「あっ、いい顔してはるなぁ」と感じるようになった。誤解のないよう申し上げると、人を呑むような物言いではなく、ただ純粋にそう感じる。とはいえ感じるようになったはたいそうであり、主観も主観、愚の骨頂にすぎない。それを承知で、「なぜ、私はあの人の”顔”をいいと思った」のか自問する。次に、「他の人はあの人の”顔”をどう思っているのだろう」と周りの見知らぬ人に尋ねたくなる。そんなことをして今の齢になって、「一種の空気」が自分のなかでしっくりくる表現として定着した。
これは、食事でも同様だ。レストランや酒場で隣人のしぐさを眺めていると、なかには「あの人のような立ち居振る舞いをしてみたい」と羨望のまなざしをおくりたくなる人がいらっしゃる。しゃちほこばったり、めかしの度をこえているわけでもない。はたまた奇をてらっていない。とにかく溶け込んでいる。溶け込んでいるのに、その周りの空気だけ異彩をを放っている。そんな「矛盾を抱え込んだ秩序」がある、ような気がする、だけか?
文明とは、文化とちがって、生きるマナーのことである。生き方のスタイル、と言い換えてもよい。マナーの確立とは、だから、生き方のスタイルをもつということである。少しばかり大げさに言えば、食は文化であり、食べ方は文明である。食をつくることは他人にまかせても、その食べ方は自分のものでなければならない。なにしろ、立派な文明なのだから、母親のしつけも重要な存在理由をもつのである。同P.233
テーブルマナーをなにひとつ犯さずに食べても「不自然な印象」を抱かせる人もいれば、赤でも白でも自分の好みの葡萄酒を呑んで”サマ”になる人もいる。これらはいずれも瑣末なことだけど、この瑣末から匂い立つ香が辺りを包み込む「雰囲気」が「顔」を持つ人にはあるのではないか、と食事中、口惜しくなる。
「顔」をもって、「食」の立ち居振る舞いがある。そして最後につながって点が線になった。それが「スタイル」だ。本書に引用として登場するタキという名のギリシャ人の「スタイルとはなんか」の一説。以下、孫引き。
スタイルという言葉は、英語の中で最も濫用されている言葉である。だいたい無意識な人間は、”ファッショナルブル・ピープル”がスタイルをもっているのだと考えている。
だが、スタイルとは捕らえどころのない資質であって、上流社会の人間やトレンディの大半は、本物のスタイルなどまったくと言っていいほどもち合わせていないのだ。
スタイルは、金で買うことはできない。
コンサイス・オクスフォード辞典は、このスタイルを、きわめて優れた資質として定義しているが、要は抽象的な性格のもので、もっている人はもっているし、もっていない人はもっていない。ただ、それだけのことなのだ。
とはいえ、今日くらいスタイルが欠如している時代も珍しい。とりわけ、人の上に立つ層にそれが著しい。世界最強の国の大統領ジミー・カーターが、選挙用の自己のイメージ作りに世論調査機関やイメージ・メーカーたちの助言にすがる有様など、まさに現在のスタイルのない世界を象徴する出来事といえるだろう。
社会学やPR活動の専門家がこれほどまでに当てにされるということは、自己の内部に信念(コミットメント)がないことを如実に物語っている。
つまりは、スタイルがないということだ。
スタイルとは見せかけの反対である。
強い信念のことである。
ひっきりなしに葉巻を喫い、痛飲を重ね、意地の悪いことで有名だったウィンストン・チャーチルは、本来的には下品な男だった。にもかかわらず、その実行力と強い信念が、彼を確固としたスタイルの持ち主にしていた。今日ではスタイルをもつ政治家は皆無に等しい。少しはスタイルを持っていた最後の政治家は、ジョン・F・ケネディだろう。
スタイルの特徴(のひとつ)は、深みのある人格が知らず知らずのうちににじみ出て、なにもしなくてもいつの間にか、まわりの人間の関心を集めている、という点にある。
[…]要するに、本物(オーセンティック)たらんと意識的に努力しなくても本物たりえている人間は、だれでもスタイルをもっているということだ。さらに、家柄などどうでもよく(財産も)、個々人の生きるスタイルこそ重大なのだと信じている人間がいる。彼らもまた、スタイルをもっている。
「顔」と「食事」と「スタイル」がなにやら一体となってべっとりまとわりつく。不思議な感覚に襲われる。老若問わず、眼前の「顔」をもつ人は、みな、目にみえるかたちで加齢していく物理的な”何か”をもっている。何かは、しみや皺であり、たるみもそうだろう。他方、”過去”の目に見えない”何か”が、これらの人の「顔」の”現在”として出現させる。わたしには、可視化できない”何か(=過去)”はいっこうにわからないにもかからず、可視化できる”何か(=現在)”で判断しようとしている。
まったくもって私だけの私しかわからない私のくだらぬ主観であるけれども、なぜ「そのように判断したがる自分」がいるのか、それが不思議。おそらく単なる無知の嫉妬なのだろう。いや、嫉妬でないか。嫉妬は、「失うかもしれないという恐怖から生じる」感情であるならば、私は一度も「顔」を持ち得ていない。その点、愚昧の羨望なのだろう。なるほど、だから羨望は七つの大罪のひとつであるわけか。