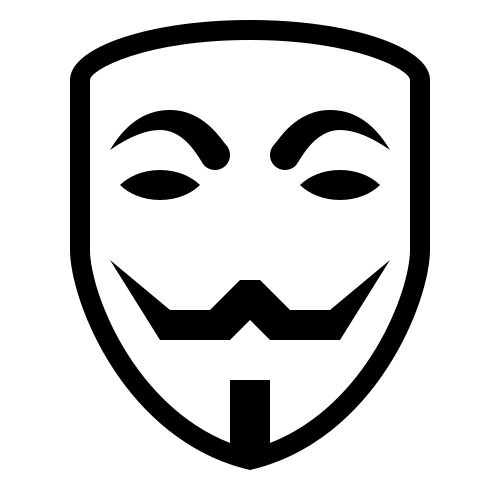一つ前のエントリーで東京ファイティングキッズ・リターンを紹介した。「リターン」なので帰ってくる前がある。それが本書。内田樹先生と平川克美氏の往復書簡がまとめられている。手段は電子メール。思考の拡散と収束を繰り返し、「時間」という概念が伏流した抽象的対話が綴られている。リンク先のAmazonのカスタマーレビューは表層的印象として的を射ている。しかし、私はそれらを参照して奇妙な溝を感じた。その溝の正体はわからない。愚考すると、「対話」のとらまえ方なのかもしれない。「対話とは、齟齬をきたすことなく”わかる”もの」というのがカスタマレビューの前提なのかもしれない。他方、「対話は齟齬の連続であり、自分がいかに誤解しているかを確認して伝達する”わからない”もの」と私は愚考に愚考を重ねる。「わかる」を前提にしている読み手からすると、「抽象的。テーマはアメリカ・外交問題・世相・大学に絞られている。だったら、すっきりわかりやすく述べられるだろう」になり、「めずらしくかみ合っている」となるのではないだろうか。
自分の組織の脆弱性や、戦略の不適切性についてのチェックには耳をふさいで、いいところだけを吹聴してまわるというのは、いずれ倒産する企業の経営者に典型的なふるまい方であるということは「知識」としてはみんな知っているはずなのに、同じ基準が自分自身についても適用される可能性には思い至らないというのは、モラルの問題である以上に知性の問題ではないのでしょうか。東京ファイティングキッズ P.152 内田「ここに難問あり」ということを示す”アンダーラインを引く”
臆断すれば、人のふり見て我がふり直せか。それができない原因を「知性の問題」と指摘した。その知性とは何か?『ためらいの倫理学』で述べている。
私は知性というものを「自分が誤り得ること」(そのレンジとリスク)についての査定能力に基づいて判断することにしている。平たく言えば、「自分のバカさ加減」についてどれくらいリアルでクールな自己評価ができるかを基準にして、私は人間の知性を判定している。ためらいの倫理 P.145
自己評価とは自動車の車検みたいなものである。「タイヤの空気圧低下・ブレーキランプ切れ・バッテリー交換」という指摘を受けた私が、その後直したかどうか尋ねられたとき、「カーオーディオの音質は最高です」や「レザーシートは抜群です」と回答したら、相手はどう反応するだろう。「そのまま走ると事故する」という注意に対して、「そんな話は聞きたくない」と耳をふさいでいる。
顧客満足度調査をする企業がある。”やる”こと自体の是非を論じるのは大切だと思う。さらに”やって”みなければ何もわからない。ただし、そのとき、「なんのためにやるのか?手段と目的が本末転倒だ」なんて野暮を私は口にしない。それよりも問いかける。「自分のバカさ加減を査定できているのだろうか」と。すると、顧客に問いかける質問がおぼろげにつかめてくる。
回答者の私は質問を見ると、「ほんとうに”満足”だけを知りたいのかもしれないなぁ」となかば嘆息してしまう。表面的には「顧客のために」であっても主語は「私たちの会社は」である設問は答えにくい。自戒をこめると、「知識」を持っている人が集まっている組織は、質問も「知識的」なのではないだろうか。質問自体が形式知に登録される。一度登録された形式知は「社内の常識」として固定する。
『ためらいの倫理学』のあとがきではこうもある。
自分の正しさを雄弁に主張することのできる知性よりも、自分の愚かさを吟味できる知性のほうが、私は好きだ ためらいの倫理学 P.349
「自分の愚かさを吟味できる知性」を私はまだ知らない。どうすれば体得できるのか糸口すらつかめていない。それでも何度も何度も読み返した結果、本書と東京ファイティングキッズ・リターンに抱いた不満を一点のべる。
それは、「歳をとる(老いる)こと」と「世代をとること」を一部混淆しているのではないかと疑った点である。
両書には、「歳をとらなければわからないことがある」や「歳をとって今までは違ってわかった」といったフレーズが散見される。それは、もちろんそのとおりだと思う。だから私は今から歳を重ねるのが楽しみだし、逆に、ただ歳をとりたくない。この「あたりまえの事実」を咀嚼するから一日の長があり、うらやましくもあり、その歳から眺めた今の私たちがどう映るのかに耳を傾ける。私には想像しようもない歳を重ねた人たちの言葉からにじみでる「あわい」を遊弋する。
しかし、「世代をとる」はそうではない。ある世代特有の事象、「オレはガンプラで遊んだ」や「CDとレコードの両方置いてあるレンタルレコード屋に通った」とかは事実でもあり模造記憶でもある。その世代が媒介を通じて共有しただけにすぎない。そしてその世代の穴から「現在」をのぞき込むように語る口調に私は賛同できない。
本書には、歳をとった両氏の金言がいつしか世代をとった二人の会話に変換されているときがある(と思う)。もちろん、叡智の人である御仁が自覚していないわけがないだろう。以上は、私の主観から生じた印象であり、これを固定させると「自分の正しさを雄弁に主張することのできる知性」になるのかもしれない。だから、愚生は自分の愚かさを吟味すべく両書の対話に交えてもらい、再読を重ねる。
関連エントリー: