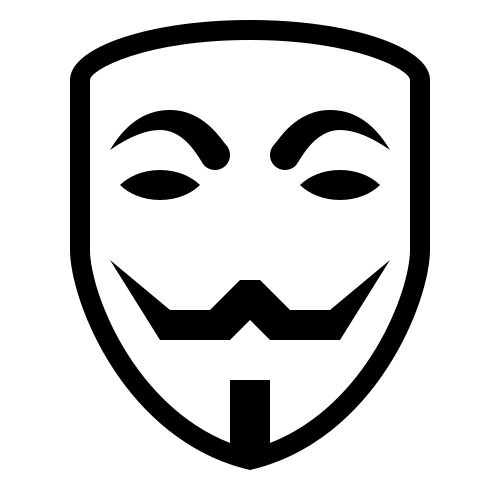平川克美氏のブログの「島の命運」と内田樹先生のブログの「テレビが消える日」、そして少し前のエントリーだけどMeine Sacheさんの「詐欺師の告白」をあわせて読めば透けて見えてくる。何を透かそうとするのか?
「都市銀行の利益といっても、俺たちの利息を掠め取っているだけじゃないか」と嘆く人が多いかも知れない。ただ、この度の都市銀行の利益の中身を見てみると、貸し出し利息による収益は縮小しており、利益の多くは国債や債権の売却益によるものらしいので、上述の「民衆の嘆き」は必ずしも当たってはいない。グローバリズムの進展の中で、金融テクニックを駆使して儲けた金である。バンカーズの不人情を恨んでもしょうがないのである。かれらとて、国際金融市場で切った張ったの闘争をしている。裏を返せば、貧乏人からはしぼるだけしぼってしまえば、もう用はないといったところで、もやは、貧乏人はマーケットの中で相手にされていないといったほうがよい。カフェ・ヒラカワ店主軽薄 「島の命運。」
「俺たちの利息を掠め取っているだけ」の銀行は「空前絶後の利益」を計上したにもかかわらず顧客へ何も還元しない———-テレビのスイッチをいれると、誰かが力説している。はじめて耳にしたとき、口をアングリとあけたまま「わざと言っているのだろうか」とキャスターを凝視した。マスコミに勤務する人なら決算書を手に取れば、カラクリは一目瞭然のはず。民衆の嘆きは当たっていない事実を説明する気配はない。そして、テレビのヒトは、「貧乏人はマーケットの中で相手にされていない」と告知しない。なぜか?
今のテレビは、いくら時代が進歩しても多分人口の3割くらいは常にいるであろう、テレビのことを鵜呑みにする人=「だまされやすいバカ」を感動させて集団で動かし、社会全体を巻き込む渦巻きを作って銭を搾り取る装置です。
かつては、それ以外の「7割の人」をいかに取り込むかにかなりの力を入れていたと思います。しかしネットの普及などで「7割の人」におけるテレビの影響力は劇的に薄れ、もういくら「7割の人」に向けてメッセージを送っても、打てども響かずの状態になってしまいました。だから最近は、はじめから「7割の人」は切り捨てて、「だまされやすいバカ」を徹底的に操る方向にシフトしているのです。とくにニュースのように、名目上あらゆる層に向けた番組は。Meine Sache 〜マイネ・ザッヘ〜 「詐欺師の告白」
「だまされやすいバカ」から銭を絞り取る以外にテレビの余命が残っていない。7割の人には打てども響かずの状態になっている。CMをとばして大量に録画できるHDDレコーダーを手にした視聴者もいれば、YouTubeでハイライトだけ視る世代もいる。さらにはワンセグで視る人々の「率」は現システムではカウントされない。
企業もバカではない。CMの効果がなくなりつつあることを薄々感づいている。だからコラボレーションCMや検索CM、はたまたドラマのなかにさりげなく仕込むCMといった具合にあの手この手でテレビそのものをCM化する。つまり箱の中は「広告」となっている。それを広告業界のお化け企業が司る。資金源を抑えられたテレビの中のヒトは諫言できない。
その段階で「こんなことしてたら、テレビは終わりですよ」という諫言を述べるようなまともな社員はもうどこにも存在しない。
だって、「テレビが終わる」ことからテレビを延命させるというアクロバシーをテレビはもう選択してしまったからである。
「『テレビがもうすぐ終わる』とみんな思っているだろ。みんなその『死の瞬間』を見ようとしてテレビをつける。だから、今日もテレビは生きてられる。オレらの仕事はただできるだけこの断末魔を引き延ばすことだけなんだよ。それで飯が食えるんだから、『らくだ』のかんかん踊りとおんなじだよ」という狡知が今日もテレビを延命させている。内田樹の研究室 「テレビが消える日」
おそらくテレビ自身も気づいてる。「もう違う」と。しかし、成功体験を捨てられない。デジタル技術とインターネットを活用すればもう一花咲かせられるはず。3割くらいの人が延命させてくれている間に、もう一花咲かせるべく打ち上げ花火を用意する。
私は違うと思う。技術によって「変わる」のは確かだろう。しかし、求めるコンテンツが「変わらない」。テレビを捨てはじめた人は「変わってゆくけど変わらない」ことがわかっている。視るに値するコンテンツはない。
しかし、他方もっともおそろしい事実が私に突き刺さる。「だまされやすいバカ」の3割に自分が入っていると私自身は気づいていないことだ。「まさか私が」と錯覚する。それが何よりもおそろしい。私は常に7割の側にいると私だけが思い込んでいる。その結果何がおこるのか?
「ある日、タカハシさんは、長男と一緒に、ぼんやりとテレビを眺めていた。そして、ちらりと、テレビの画面を見つめている長男の顔つきを見て、愕然としたのである。
長男は床に猫背になって座り、口を半開きにして、顎を突き出し、ぼんやりと澱んだ瞳で、画面を見つめていた。
タカハシさんは、長男の名前を呼んだ。反応がない。もう一度、呼んだ。まだ反応がない。そして、三度目、ようやく、長男は、タカハシさんの方を向いた。その瞳には何も映っていないように、タカハシさんには見えた。まるで魂が抜けてしまった人間の表情だった。」