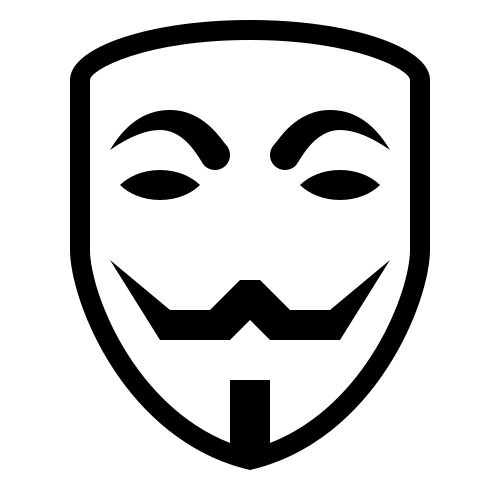ひとたび踏み込むと、深淵を覗かせる。まるでつかみどころがないけれども私たちに密着している。
ブランドの価値は、いったいどこからどのように生まれるのか?
この問いに回答を与えてくれる理論はない。一方、ブランドの価値について二つの意見がある。
- 「ブランドとは、市場で消費者に選ばれた商品である」—ブランド自然選択説
- 「ブランドの核心にはつねに、制作者や経営者のそのブランドにかける思いや夢、世界観やビジョンがある」—ブランド・パワー説
1.と2.は対照的である。どちらに正解があるわけではない。ルイ・ヴィトンやベンツは後者にあたる。
商品が開発されと名前がつく。その時点では、他の商品と区別する記号にすぎない。やがて記号が広く認知され、手にしたことがない消費者でも商品名を聞いたとき、その中身がわかるようになる。そのとき「名前」は自立する。それ自体に「価値」をもつ。すると、逆転現象が起きる。製品が名前の価値を伝達するためのメディアと化す。
たとえばポッキーは今や年間売上300億円を大きく越えるグリコのドル箱商品である。1966年に誕生したポッキーは「プリッツ」からヒントを得て。いわば派生商品。プリッツのスティック状にチョコレートをかけてみれば、子ども向け商品として新しく販売できるかもしれないとグリコは考えた。
当初の商品名は「チョコテック」。それが食べる時に、「ポキッ」と折れることから「ポッキー」というネーミングが採用された。
ここにブランドの偶然性がある。もし、このとき、すでに人気商品であったプリッツにあやかろうとして、「プリッツ・チョコ」といった名前がつけられていたら、プリッツとの差異化に成功していなかったもしれない。
その後、”ポッキー・オン・ザ・ロック””ポッキーでおもてない””旅にポッキー”と、食べ方の提案にまでおよび、生活の場を演出するマーケティングへと進化する。そして、昨年、新垣結衣さんを起用したCMが大ヒットした。
製品と名前のあいだで、メッセージとメディアの試行錯誤が繰り返される。名前がメッセージとなり、製品がメディアの役割を果たす。その反対もある。メッセージとメディアの交錯のダイナミズムが「ブランド」を誕生させる。そして、商品を育てようとする社内の強いコミットメントによって「ブランド」として成長する。
さらにブランドが文字どおり「ブランド」として独立した事象になったとき、そこにはフィロソフィーが宿っている。私は、以前から「アメリカ人はなぜあれほどコカ・コーラを飲む」のか不思議に思った。その疑問が本書によって氷解した。
「コカ・コーラ」という製品の属性を一切語らず、「本物(かわらぬものはコークだけ)」、「笑顔(コークが笑顔を生む)」、「共感(フレンドリー・フィーリング、世界は一つ)」、「ナショナリティ(アメリカを見てごらん!)」、「普遍性(コークを飲むともっといい)」といった抽象的表現があらわれ、そのシーンにただコカ・コーラがあるだけだ。味覚や喉越しを訴求するメッセージはない。それを観た人たちはやがて、そのシーンに遭遇したときコカ・コーラを飲むように導かれる。
一昔前ならスポーツの後、蛇口をひねって水をがぶ飲むする姿が青春映画に映し出された。今なら、ポカリスエットで事足りる。
私の生活に知らず知らずのうちに浸透しているブランド。それはビジネスの視点からだけでは捉えられず、いまやコミュニケーションにまで昇華されつつある。自分の身のまわりにあるモノとトレースしながら読むと、自分がブランドに囲まれていることを認知させてもらえる良書である。