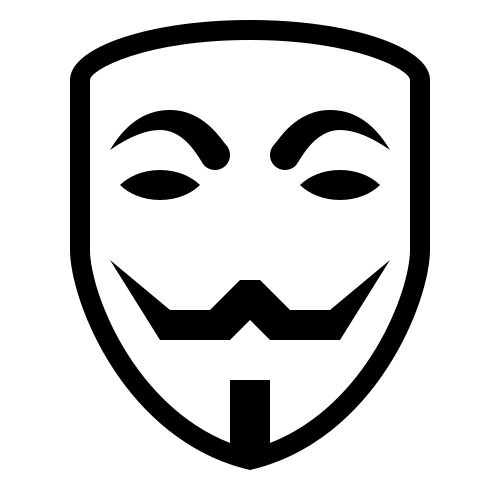TLにながれてきて鼓動がイレギュラーした。
顏の皺はじぶんでは見えない。だってもう老眼だもん(笑)。わかるのは心が蘇生してるってことだけ。魂はどんどん若返ってる。死を意識しているからだと思う。先を考えずにやりたいことをやる。子どもみたいに。
— 田口ランディ(Randy Taguch) (@randieta) October 24, 2015
死を意識しているつもりだった。していなかった。賞味期限がないアイスクリームを冷凍庫にいれっぱなしにしているように凍らせていた。
今年、「自殺とかせんといてくださいよ」とお客さんがおっしゃった。開業してはじめてのお客さん。爾来、ずっとお世話になっている。どう感謝しても足りない。スタッフの方と3人で食事しているときに軽妙な語りでおっしゃった。前後の文脈がもたらす冗談。
顔にでなかったと思う。あら、そんなふうにご覧になってくださっていたんだ。驚き。同時にその一言が意識と無意識を攪拌した。
森博嗣先生のミステリーには、真冬に半袖を着て歩いているかのように自殺が現れるてぎょっとする。動機はわからないまま現れて物語の渦に消える。登場人物に語らせて、書き手の意思が反映されるでもなく、登場人物は淡々とそれぞれを語り、フィクションとはいえほんとうに自殺したのか奇妙な感覚におちいる。自殺から顔をそむけていた。いまも「JI・SA・TSU」と入力するのをためらってしまう。どうしてだ。自殺から顔をそむけていたのに尊厳死や緩和ケアの死については関心を持って読んでいた。
さきのTLのあとだったと思う。「逢いたい人には、どんどん逢いに行った。」と目にした。すばらしい。そう感じた。心から。素直に。そんなふうに書ける人が世界のどこかでいらっしゃる。共鳴した。たとえ私はいますぐにそうできなくても、逢いに行かれたときの喜びが憑依したようだった。
毎朝目が覚めること、目が覚めるたびに私が自分であると覚えていること、それ自体が奇跡であるはずが、いつのまにか水や空気のよう。
空襲も日に夜をついでというふうに烈しくなり、娘らしい気持を満してくれる娯しみも色彩もまわりには何一つなく、そういう時代的な暗さと、自分自身に対する絶望から私は時々死を憶った。どうしなくても簡単に死んでしまうかもしれない状況の中で、私の憶ったのは自殺だった。暗い大海原のまっただなかでたった一人もがき苦しむようなのが、どんな時代でも青春の本質なのではないか? と思うことがある。それほどに自分を摑まえ捉えるというのは難しく苦しい作業だ。
でもそれさえが贅沢な悩みであっただろうことは、女学校時代の友人が女子挺身隊として徴用され、愛知県豊川の工場で爆撃死したこと、学徒出陣も始まっており、文科系の学生は否も応もなく戦地へ狩り出さされていた、ということである。『茨木のり子集 言の葉1』 P.212
後に詩人になる二十歳の先生が迎えた終戦。反対に詩人に憧れた高野悦子さんは二十歳で自殺した。『二十歳の原点』を読んだ残像は体のどこかで棲まう。ページをめくった冒頭、「独りであること、未熟であること、これが私の二十歳の原点である」と。彼女たちより倍以上の月日を経た私が正視できない正体はなんだろう。
生きている実感は特上のお寿司を食べるようなものではなく、とれたての野菜や果物をそのままいただくような、包まれるような皮膚感覚。ふとしたときに感じ、生死をさまよって心身に深く刻まれる方もいらっしゃると想像する。
実感に飢えていたか、希薄だったか。否、甘えていただけであり、陶酔していた。月が綺麗だと独りごちて確かめられるいま生きていると感じる。たしかな感覚。弱さを捨てて、しなやかで強い心を手にしたい。生きている実感は自然のうつろいに求め、奥深く微妙で細かくて、はかりしれない色彩のうつりかわりから満たしてもらおうとしていた。いまもそれは続いている。
交わる。あふれでる感情、言葉のうごめき。無二。たしかな感覚が生を包む。なによりもどこかでずっと残してくださっていたこと、そして指が動いたことに心からありがとう。