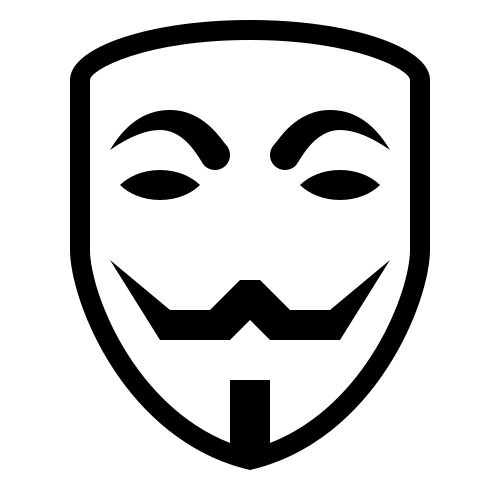「自分探し」のなかに「他人」は存在しない。「他人」が存在しない労働観が敷衍。ではひとたび消費するほう、労働者が送り出した商品を購入する立場に身をおくと「他人」は存在するのか?
「労働」とは、他人の需要に応えることである。いたって簡単なことである。他人が望まないものを作っても売っても、他人は買わない。他人が望まれないことしても、他人は喜ばない。だから、その労働が「無駄な骨折り」になって、「労働」として成り立たない。「他人の需要」があって、それに応える「供給」になった時、労働は初めて「労働」としての意味を持つ。いたって当たり前のことだが、これが「労働」の大原則である。それでは、どうしてこれが空回りするのか?
少し前まで労働と消費は「私」と「他人」を混濁していた、いや、そんなことすら考えずにすんだ。働き、必要物資を購入してわずかな余暇を家族と過ごす。
空回りをするから、労働がイコール「つまらない」になって、「自分のやりたいことをやりたい」という逸脱を生む。
それを見て育った次の担い手は、「私」なき労働にギモンをいだき、「他人」と同じ消費に嫌悪し、他人を消し去った。担い手を送り出す方も「私と同じようにしたくない」と経験なき知識をインストール。
「自分がやりたいことをやりたい」というのは、いたって当たり前の欲望だが、これはべつに「労働」ではない。この欲望のどこにも「他人」がいないからである。「他人」がいて、その他人の「望むこと」があって、それに応えてなにかを提供する—–そのことによって「代価」を得る。これが労働である。自分のやりたいことをやっても、そこに他人は関わって来ない。他人が関わって来ることを考えるのが「他人の需要に応える」で、これがないまま「やりたいこと」だけをやったって、他人は関わって来ない。これは、「無駄な骨折り」と呼ぶべきことなのだが、そう思われないのは、当人に「自分のやりたいことをやっている」という自己満足があるからである。本来なら「他人」の存在を前提にしているものが、「自分のため」になってしまっている。だからこその逸脱である。『失楽園の向こう側』 P.29
「他人」がいなくても「自分がやりたいことをやっている」と、いつしか他人が集まってきて、社会が形成された。オープンソース。その衝撃を認識できるヒトはまだ少ない。「他人」の存在は前提するものではなく、創造するという新たな担い手が降臨。
もちろん仮想の世界で蠢動した現象を現実の世界へトレースできない。だからそんなものは現実じゃないだろうと上に立つヒトたちは揶揄嘲弄。仮想と現実を二分するから不毛な議論はつづく。
これと同じ内容を書いている人がいる。内田樹先生。「労働」とは、他人の需要に応えることであるは橋本治先生か内田樹先生かどっちの著書で目にふれたのだろうか迷うほど。同世代の「観」があるのだろうか。「答えはない」と常々書いていらっしゃる点も共通。
ふと首をかしげる。なのに「労働」については、「答えはすでにでている」というか「むかしから”そこ”にある」がごとく明晰な文章を記している。那辺にあるか推し量れるはずもない。ただ「ああ、そうなのか」と。
上記の「労働」に他の単語を代入しよう。先日、商品開発やサービスについてスピーチしたとき、上記のような話をしたい自分がいた。ただ他人の需要に応えることとはどういうことなのだろう? ここから出発しようと赤貧のボキャブラリーを駆使。問いを投擲。
相手のことばは「マーケットインは大切ですよね」。成句がすうっと耳を通りすぎた。やっぱり優秀な方々はみごとに一言に集約するなぁと感じ入った。私はその”マーケットイン”のとば口にも立っていない。大切かどうかすらわからない。ただひとつ懸念が生じた。
あなたが提供しているサービスに他人がいているのか?を認識して自分のやりたいことをやっているのか? それだけ。
同時にこの懸念は眼前の人を斥力にして私に向かってくる。
自分は既に結婚している。「”妻が一番”であってもかまわないが、不倫相手の”こいつ”がいたっていいじゃないか」という気にもなる。なってしかし、結婚してしまっている男には、不倫相手、あるいは浮気相手の”置き場所”がない。大っぴらに家に連れて帰るわけにもいかない。会社の同僚であるのだとしたらなおさらで、会社では大っぴらな関係を提示出来ない。結婚してしまった男から会社と家庭を除いてしまったら、もう居場所というのは”その他”というところにしかない。”その他”というところに浮気相手を置いて、それで自分はホッとしている。だとしたら、その浮気相手と共にホッとしている「自分」なるものの位置付けは、「その他のところに存在する余分」である。つまり、「自分」というものは「余り」なのである。同P.164-165