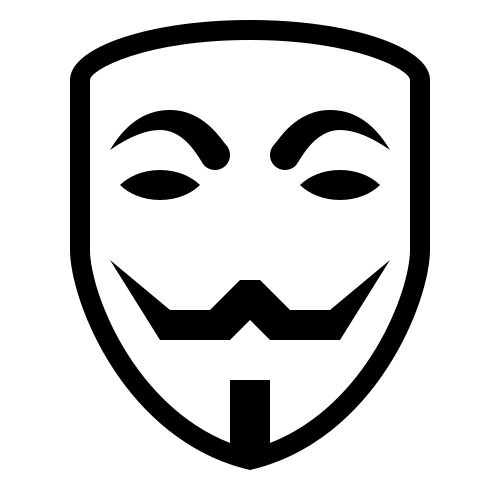今にはじまったことではないのですが、医療情報についての医院サイトとユーザーとの間に「情報格差」がまだまだあるという結果です。
japan.internet.com: 医療情報サイト、もっと情報を!!——大半が検索エンジンから
この調査結果の
医療情報サイトを知るきっかけとなったのは、 前回同様「検索エンジン」が圧倒的に多く(269人)、「新聞、雑誌」43人、「口コミ」(29人)に大きく差をつけた。雑誌やその他のネット以外の媒体とサイトとの連動は進んでいないようだ。
ですが、これは医療情報サイトのビジネスモデルが
- 医院からのサイト登録、有料サービス、広告宣伝費が収入源
- できる限りランニングコストをおさえる
- 1と2の要素を両立させる最適な営業手段は、SEOに注力する
ことから、現在では医療情報サイトが各検索エンジンの上位を占めるようになっています。ですから、ユーザーにとって医院を探すには便利ですが、医療情報そのものは、あまり有益な情報が掲載されているとはいえません。
それ以上に、重要なことは下記の点です。
サイト自体に関する不満な点として、「内容が難解すぎて理解できない」をあげたユーザーは62人だが、一方「知りたい情報が不足」しているをあげたのは131人もいる。
歯科医院のサイトをお手伝いしていると、この問題は最重要課題にあげられます。例えば症例のページを作成することを考えてみます。このとき問題になるのが、先生方の説明文章です。
その内容は、受診者よりもむしろ学会・スタディーグループの先生方が閲覧されることを意識されている場合があります。そうなると、症例ページは専門用語で構成された学会のプレゼン資料になりがちです。では、平易な言葉で説明しようとすると、色々微妙な問題も含んでいるようです。このあたりの痛し痒しの問題は、先生方のお考えをお聞きしていると納得できることが多々あります。
しかし、それもで「ウェブサイトの目的」で述べましたように、「何のためにウェブサイトを作成しているのか?」という原点にかえることが大切だと思います。
この受診者(ユーザー)と医院との間にある「情報格差」には、「お互いが聞く・話す・知る・覚える・見る」というアナログ的コミュニケーションが少し足りないことが原因のひとつと、私は考えています。
なぜなら、私のお客様の先生方の話をお聞きしていると、アナログ的コミュニケーションが、しっかりとできていればいるほど、サイトの情報の質と量が充実しているからです。
- なぜ、この医院を選んだのか?
- なぜ、この段階で来院しようと思ったのか?
- 今までの治療での出来事にどんなことがあったのか
- どんなライフスタイルか?
- ふだん、何に気をつけているか?
などなど、簡単なことから込み入った話まで多岐にわたります。そして、「聞く・話す・知る・覚える・見る」には、技術を習得したり道具が必要であり、なによりも俗に言う「人の資質」が大切です。そのために研修やミーティングを重ね、試行錯誤を経て最適化していき、ようやくオリジナルの院内システムが構築されると、先生方によく教えていただきます。
その院内システムから収集された「受信者のアナログ情報」を加工してウェブサイトに掲載するのが「デジタル情報」です。これが、私がよくお話しする「デジアナ」です。サイトは「デジタル」、中身は「アナログ」です。
アナログは探せばいくらでも見つかります。「一人一人の来院者の物語」「スタッフの物語」「院長先生の苦労話」「こどもの苦労話」「待合室の風景」など、まだまだたくさんあります。
今回のような調査結果を見ていると、「医療情報の需要と供給の格差」をまだまだ是正し、SEOをしていけば、来院につながるサイト作りをできるのだと思います。