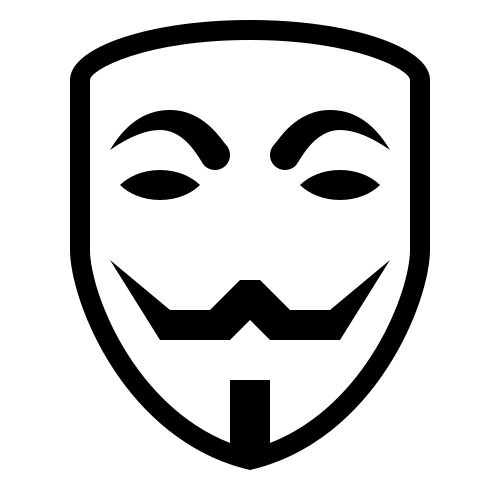予言であるならば耳を貸すのはおっくうだが、ふれてしまった以上、じたばたしてもはじまらない。あらがうことなくまずは受け入れよう。天空が指ししめす変化を地上でも指摘する人がいる。幻想と現実を「対」とする表象が描かれれば、迷う道筋は少なくてもすむかもしれない。
予言であるならば耳を貸すのはおっくうだが、ふれてしまった以上、じたばたしてもはじまらない。あらがうことなくまずは受け入れよう。天空が指ししめす変化を地上でも指摘する人がいる。幻想と現実を「対」とする表象が描かれれば、迷う道筋は少なくてもすむかもしれない。
「予言のことばを借りると」ティーピングは言った。「いまわれわれは大いなる変化の時代にいる。千年紀が少し前に終末を迎え、それとともに、占星術で言う二千年に及ぶ魚座の時代が幕を閉じた。魚はイエスの記号でもある。占星術にくわしい象徴学者ならだれでも知っているが、魚座の理念では、人間は自分で物を考えることができず、より高次の存在から行動の指針を教わる必要があるとされている。だからこそ、この期間は熱心な宗教の時代だった。ところが、いまやわれわれは水瓶座の時代に踏みこんだのであり、その理念は、人は真理を学び、おのれの力で考えることができるというものだ。いわばイデオロギー上の重大な変革で、いままさにそれが起こっている」『ダ・ヴィンチ・コード(中)』 P.198
内容はよくわからないが、引用箇所だけが印象に残った。右の説とリンクさせた。同様に少し長い。
二十世紀が終わって、人間は再び過去の次元に戻った。そこでは、困難を切り開くものは、常に「自分の力」だった。「自分の力」がふるえるようになる前に、「どうしたらいいのかわからない、なにがなんだかわからない」という混迷に呑み込めれても不思議ではない。人類は常に、そういうところからスタートしてきたのである。[…..]「どこにも正解がない」という”混迷”の中で二十世紀は終わり、その”混迷”の中で二十一世紀がやって来た—–そう思ってしまったら、もう二十一世紀は終わりだろう。「わかる」からスタートしたものが、「わからない」のゴールにたどり着いてしまった。これが間違いであるのは、既に言ったとおりで、であればこそ二十一世紀は、人類の前に再び訪れた、「わからない」をスタート地点とする、いとも当たり前の時代なのである。『「わからない」という方法』 P.25
橋本氏は二十世紀を「”わかる”が当然とした時代」と定義した。もし自分がわからなければ、「正解」がどこかにあると思っていた世相だった。だから、「理論」へと走った。「理論がある」を前提としているがゆえに、「知らなければ恥ずかしい」といった塩梅となる。
しかし、そうでなくなったと両者が述べている、ような気がする。頭がわるいのでよくわからない。語感の印象だけで断をくだしている。文脈の背後までせまれていない。
両方ともわからないとはいえ、かろうじて掴めたと思うことが一つある。それは、書かれている「単語」の意味は明瞭なのに、各々の単語が連結するとわからなくなるのはなぜだろう、ということだ。
「おお、そうなのか」と腑に落とし、のちに「ほんとうにそうなのか」と小首をかしげ、あとは凛とすれば、たじろがずともよい。