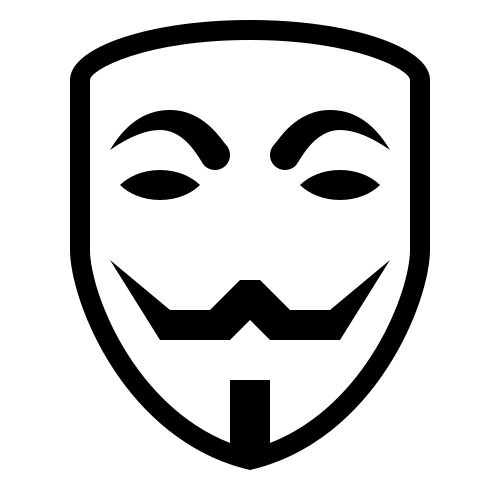2015.01.04 晴れ
野村萬斎さんと辻井伸行さんの言葉は通底していた。野村萬斎さんは自分の狂言、辻井伸行さんは自分の音。「自分の」表現。エゴイズムなニュアンスとして受けとっていない。型の通り表現される方がある高みまで達して立ちはだかる、孤高の悩み。そう感じとった。高みを想像できないし、どんな領域だろう?
「自分の」であって「自分だけの」ではなさそうだ。誰かと比べたくなるから「だけ」が付く。比べない。比較の発想はない。「何か」をひたすら追い求めて精進する。何かは自分にしかわからない。自己との対話。
カメラを持って散歩へ行く。光と影を探す。近ごろは曇りも楽しい。曇りだと入念に光を探す。明暗差がなければどう撮ったらよいのかわからない。だからおもしろい。写真をiPhotoにインポート。くり返し見る。撮っているときに感知していなかったことがわかる。どうしてその時に認識できなかったんだろう、って苛立ち、その時の動作を思い出す。不思議なほど思い出せない。明らかになってくる課題。
あとから見て印象に残るか残らないかは、見る時の心情によって左右される。気になってシャッタを押しただけの一枚が、たいてい印象深い。上手く撮りたいと欲張る。欲張ればできあがりは拙い。目も当てられない。被写体を前に迷う。考えるのではなく迷うのだ。被写体よりもカメラに気を取られる。被写体を見ていない。目に映るモノやコトと、写真は違う。実感した感覚である。違う。たとえばテーブルの上にリンゴをのせて撮る。被写体のリンゴと撮影したリンゴは違う。
なぜ違うと感じるんだろう? 切り取るからかしら。視覚に入る色や形、陰影、奥行きが平面の一枚に収められる。切り取らなかった情報量(テーブルの端や床など)は頭の中に残っている。明瞭な残像はなく、朧気なイメージ。見ているようで見ていなく、見ていないようで見ている(らしい)。視覚にあっても見ていない情報もひっくるめて眼前のリンゴを知覚している。
二つの映像は違う。だから心象か写実かと論争し、主義にまで昇華される。写真は目の前の被写体を超越しない。いまの自分はそう思う。
琵琶湖の撮影。目の前の琵琶湖より綺麗に撮ろうとする。拙い写真が量産される。デジタルカメラのデータは0と1の集積だから、撮り方を間違えなければ自在に加工して綺麗にできる。実際、色鮮やかな写真が好みの人は「自分だけの色」を追求して仕上げる。
雪が残る公園を歩く。昨年から樹木の根が気になっているから下ばかり見ている。樹木の根の雪は解けていた。円を描くように解けて現れる地表。どうしてだろう? はじめから積もっていない? そんなことないな、たぶん学校で習った自然科学の法則で説明できるんだろうなぁ、と自問自答しながら歩く、撮る。とても恥ずかしいことを知らないかもしれないし、そうだとしても知らなかったんだからしょうがない。開き直ったり、散歩しながらも忙しい。
雪が残ったままの公園。見慣れている場所もはじめて見るようでうれしくなった。雪が残っているだけで視覚が増感されたような錯覚。枯れた紫陽花の薄茶と雪の対比が映える。白の魅力。
滋賀県にも雪深い地域はある。余呉湖では1m以上積もったらしい。大阪から引っ越してきて、雪が降ることに驚かなくなったけれど(最初はほんとに吃驚した)、雪深い地域ではないから雪の公園は非日常だ。見慣れていない。日常と非日常の中間に、発想の暗示がある。