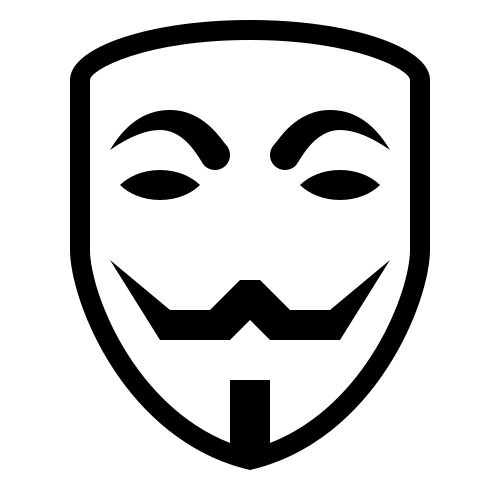批判と自己言及のつづき。
「批判」は商品になったのかもしれない、と書いた。違うなぁと思いつつ。書いた。ケツふかなきゃ。統計なんてない、単なる感覚。ひとむかし前、「言葉はチカラ」があった。喧伝した新聞社の系列テレビは「言葉のチカラ」を誇示。誰かに「消費」させるために(参照: 古舘伊知郎氏はネタにされて視聴率を稼ぐ 報道ステーションの戦略)。
批判する人(当然私も含めて)の強みは言葉の主人が「自分」である点。批判はそれ自体なにも創造しない。創造をスルーして立て板に水のごとく単語を紡ぐ。何を批判して、あるいは何を話すか、すべてあらかめじめ理解している。予定調和。だから、批判している最中に「自分の声に耳を傾ける」仕草はない。自分の声が他者に届いて、やがて他者を起点に自分へ帰還するなんて夢にも想像しない。
私が畏怖する人々は共通している。創造。オリジナリティーじゃない。無から有、有から有、どちらでもかまわない。創造する人の言葉は「言葉」が主人。「自分」じゃない。だから、自分が次に何を語るかわからずにめちゃくちゃ。でも、その言葉が他者を魅了する。創造する人の入力と出力は一対一の関係にあらず。
言葉が私の主人
「言葉」を表現手段にしてしまうと、言葉をあやつる<私>が表出する。脳が司る。身体を動かせば気づく。言葉は欲望と絶望、不信と信頼のコイン。言葉が表現手段なら言葉にできないとき「何を」批判するのか。そもそも批判を構築する思考は調達されるのか?
言葉が私の主人で、言葉は私を閉じ込める。私の空間は「言葉」に囲われている。その囲いの外側から私を眺めようとしても、それは「言葉」の外側にある。
一番最初に言語を発した人は何を発声したのか私は知らない。「言葉」が持つ絶対不可視の出発点。
言語の境界が私の世界の境界
われわれに考えることのできないものをわれわれは考えることができず、したがってまた、われわれに考えることのできないものを語ることもできない。[…]世界とは私の世界である、ということは、言語(私の理解する限りでの言語しかない)の境界が世界の境界を示すという事実に現れている。形而上学的な主体は世界に帰属するものでなく、世界の境界なのである。論理哲学論考(ちくま学芸文庫) P.168
ラッセルの序文。論考もさっぱりだし、この序文もチンプンカンプン。まいった。思考をそのままパクった。
ただパクっただけでは芸がないのは承知。でもパクってやる。そして書きながらまたとんでもない批判が浮かぶ。
「自分の言語の境界が世界の境界」であるという認識を獲得させてくれるのは他者との対話であり、他者は「言葉の檻」から私を脱出させてくれる鍵をもっている、なんてね。あるわけないか。
他者との対話に絶望があり、その絶望の向こうに<私>を理解する欲望があるのじゃないかな。