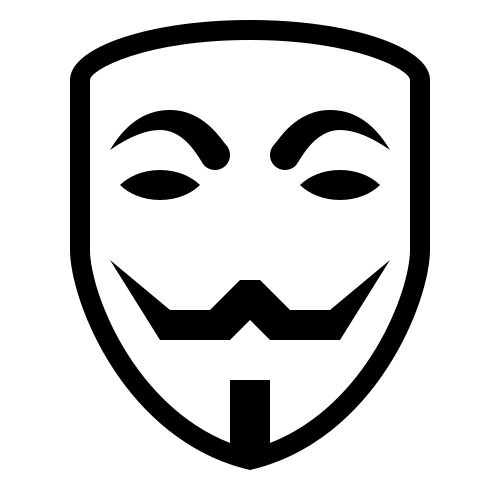「二項対立」を考察するだけで一冊の新書になってしまった。それほど「二項対立」は呪縛なのだろう。私の素寒貧の想像力をブートして、「二項対立」だけで一冊の新書を上梓する筆力と知性をのぞき見ようと試みる。もちろんわからない。ただ、ひとつ設定できたこと。問題は誰にとっての呪縛か。
敵と味方のいずれかが最初に「二項対立」を仕掛けたにせよ、「敵か味方か」の「二項対立図式」の白黒レンズを通して「世界」を見ることが習慣化してしまうと、「味方でない=敵」あるいは「敵でない=味方」と、自動的に判断することになりがちだ。そうやって自動的に処理した方が、複雑に考えて思い悩む必要がなくて、安心できるからだ。誰だって、敵をできるだけ早くより分けて、味方の中に身をおいて安心したい。そういうより分けを急いでしまうと、後で—–自分自身にとって—–取り返しのつかないひどいことになっているのに気づくかもしれないが、そうなってもいいいから、とりあえず安心したいという心理もある。
“会社”を考えるとどうなるか。ただし、大企業にお世話になったことがないので大企業の実情は知らない。私がもちだす”会社”は中小企業。テーブルに□を描く。その□が会社という枠組み。□のなかに○と●を交わらないように記す。○と●が二項対立。ひょっとすると派閥というのかもしれない。派閥なら二項対立ではなく多項対立なのだろう。無謀な設定だが強引にすすむ。ここでふと立ち止まる。「なぜ私は○と●を□の中に記すことができたのか?」と首をかしげる。はじめから「会社」という枠組みがあって、○と●の二つの集団があると自ら設定したからだろう。はじめから「二項対立」という図式が存在していることを○と●のなかのひとが気づくのが初手。「「二項対立」を”見聞したことない”人」は本書を手に取る機会がない。
○のなかの人が●に気づかない、もしくは●のなかにいる人が○に気づかない。であるにしてもとにかくどちらかが「相手」に気づけば交わりはじめるための「第一歩」がふめる。ようやく出発点にたつ。が、ここでも立ち止まる。「”○(もしくは●)が交わってないと気づいた”ということを”なぜわかる”のか」という疑問。自己言及のパラドックス。
さまざまな「客体」を認識している「主体」としての「私」自身も、”客体”の一つとして扱おうとすれば、「私を認識している私を認識している私を認識している私…..」と続いていって、「客体としての私」とは何かを確定することができなくなってしまうのである。しかもこの無限の自己反省の連鎖に出てくる「私」同士は、「記憶」による再現前化によって「過去の私はそう思っていたと、今の私は記憶している」というような不確かな形で緩くつながっているにすぎず、「私」という”存在”の同一性が保証されることはない。そして、「私」の存在が不確かである以上、「私」によって認識される”客体”の方も不確かになる。同P.168
こんなところに詰まりだしたら会社経営なんてやってられねぇって感じだけど、まぁ、頭の片隅にとどめておくのも吉だと思う。「客体としての○(もしくは●)」は不確かであると認識していれば、相手を「排除」するよりも「交わる」を選択する可能性が高くなる。「不安定なわけないじゃないか」とか「私の○(もしくは●)は確かなモノだ」と固定してしまえば、次に「排除」や「無関心」がやってくる。私の○(もしくは●)が確かであるのだから、自ら壊そうとする負荷を選択しない。会社のなかでそんな非効率的なオプションに賭け金をおかない。
ところがそんな非効率的なオプションに賭け金をおかず、かつ二項対立にも背を向けるような人もなかにはいる。
アイロニー的な態度を取る「批評」には、二項対立の両極のいずれからも距離を取った”ニュートラルさ”を志向する性質があると言えるが、それは決して両極から等距離の中間あるいは中道を目指すということではない。むしろ、どういう位置が「中間」か本当のところは分からないということを自覚しているのがアイロニーの精神であるし、「真ん中」にこだわるというのは、そもそも”両極”の存在を自明視していることになるので、アイロニーに徹しているとは言えない。[…]アイロニーは、「私の対象」に対する「私」のまなざしにズレを生じさせることで、「私」自身の存在を捉え直すことに主眼を置く営みである。同P.200,206
アイロニーが何であるのかは難しすぎて私にはまったくわからない。ただ字面をおってイメージする。と、「会社」の枠組み□のなかに○と●の二項対立があって、そのなかで”「中間」か本当のところは分からないということを自覚している”ニュートラルな人がいることなのだろうかと愚考する。
すると、ふと得心する。結局、こういう”ニュートラル”な人が「会社」という枠組みのなかで異端や異才であったりして「デキる」人と評される。が、それも「会社」をとっぱっらってはじめから「枠組みを描ける」ようなお気楽な私から眺めると、”ニュートラル”な人は、「会社」という枠組みを外しても「デキる」人であり続けるのだろうとひとりごちた。
そして、そういう”ニュートラル”な人は「会社」という枠組みのなかでは「気づかれない」のかもしれないと合点が行った。